2
当初は一晩、マンションで過ごし翌日に神社の離れを整理し、そっちに移ってもらうはずだったのだが、なぜか彼女はまだここにいる。
アスカ曰く、力の目覚めていない勇者様をお守りするためにお側から離れるわけにはいかないとのことだった。
一晩かけたカイトの説得も空しく、結局なし崩し的に彼女と同居することになってしまった。
それはそうとアスカが来てからカイトの生活環境は衣食住共に改善された。
まずは衣。今まで一週間に一度のペースだった洗濯が毎日になり、さらにアイロンかけのおまけ付き。洗濯物はいろいろと問題もあるのでアスカの担当となった。
続いて住。乱雑だった部屋が片づけられ、二日に一度掃除するようになった。
これは自室以外は二人の交代制に決定。
そして、食。これが最高に改善された。
まさに天と地。月とスッポン。ウサギと亀。これは違うか。
ほぼ一人暮らし状態が長い上に日頃からプラモデルで鍛えた指先のおかげもあってかご飯、おみそ汁、カレー、シチューと言ったキャンプの定番メニューだけはカイトも普通に作ることが出来る。だけど、それ以外は台所と味の保障が無い。
一方、アスカはカイトと違ってレパートリーも豊富な上に料理が『ウマイ』のだ。
居候初日に作った肉じゃがとほうれん草のお浸しでカイトを泣かせてしまったほどだ。それ以来、料理は完全無欠にアスカの担当となった。
カイトは思った、さらば、インスタントの日々よ、と。
順風満帆に見える二人の同居生活だったが一つだけ問題があった。
世間体と言うやつだ。年頃の男女が一つ屋根の下で暮らすのは流石にまずい。
これは誤解を生まないようにするのはかなり難しい。
居候や同居は何となく響き的に和やかな家族的な雰囲気がある。
しかし、同棲となると事情は変わってくる。年齢によって憧れと背徳の二つに完全に別れてしまうからだ。カイトとアスカは高校生。明らかに後者に見られる。
いくら、有馬が連れてきたと言っても、同棲と言う事実は揺るがない。
そこで立案されたのが、『同居だけど住所は別よ作戦』だ。
元々、双樹家はマンションの二部屋分を使用している。
つまり、二つの部屋を分割している壁を破壊し、一つにしているのだ。
カイトが以前通りに『702号室』で、アスカが『703号室』に住んでいる事にすれば、書類上は別々に暮らしている事にある。
知っている人が見ればすぐに分かることだけど。
もっとも、空いている部屋がここしかなかったというのが同居に承諾する最大の理由だったりするのだが。
アスカが双樹家にやってきて早四日が過ぎ去った。
彼女はずっと前からそうしていたかのようにシャカシャカと買い物袋を鳴らしながら階段をあるペースで上っていく。鼻歌がリズムを作り出している。
四階の踊り場で川崎さんとこの奥さんに遭遇。
「あっ、こんにちわ」
と、笑顔で挨拶をする。
「こんにちわ。今日も冷えるわねぇ」
挨拶を返す川崎さんとこの奥さん。
「そうですね。それじゃ」
再び、一定のペースで階段を上り始めるアスカ。
アスカの背中に川崎さんとこの奥さんは妙な違和感を感じた。
そして、次の瞬間、川崎さんはあることに気付いた。
あの娘、誰かしら。見たことのない顔だけど。
当然である。つい四日前にやってきた新人さんなんだから。
その疑問はおばさんの持つ特殊技能を発動させるのに十分な刺激を持っていた。
川崎さんとこの奥さんの瞳に何処かで見たような輝きが宿った。
その瞬間、彼女はただのおばさんではなかった。
アスカはポケットの中から鍵を取りだした。
カギにはこの前カイトに貰ったとあるゲームキャラのキーホルダーが付いている。
扉を開けた。
「ただいま〜」
帰宅を告げる声に続き、扉が閉められる。
それの光景を階段脇から見ている者が一人。
そう、川崎さんとこの奥さんだ。
「いいもの。みっけ」
一度唇を嘗める。
そして、ネコバスのような笑みを見せる。
「そうか、そう言う事ね」
一人納得する川崎さんとこの奥さん。
この人の頭の中ではもう、すでにストーリーが出来上がっている。
さすがは学生時代新聞部に所属し、卒業後三流紙の記者をやっていた経歴は伊達じゃない。彼女の勝手な推測に振り回された著名人は数知れない。
そこへ杉下さんとこの奥さんが通りかかる。
「あら、川崎さんとこの奥さん。こんにちわ」
「こんにちわ。ところで、杉下さんとこの奥さん。知ってましたか?」
「何がです?」
「カイト君の事ですよ」
「また、エレベーターに閉じ込められたんですか?」
この情けない事件はすでにアパート中に広まっている。
「違いますよ。カイト君、部屋に女の子を連れ込んでいるみたいなんですよ」
「もしかして、あの見かけない女の子の事かしら?最近じゃ、珍しい礼儀正しい娘ですよねぇ」
「そうよね。でも同棲はダメですよ、同棲は。ここだけの話し、私思うんですけどね」
この『ここだけの話し』と『私、思うんですけど』が危険なのだ。
時が経つにつれて、尾鰭が付いて怪物になってしまうのだ。
「多分、大家さんがカイト君の将来に不安を抱いて、どこかの山奥の村から善良だけど世間知らずのあの娘を舌先三寸で連れてきたんですよ。普段はのんぽりしているカイト君もやっぱり、年頃の男の子だし。その夜はやっぱり」
「既成事実を作ろうと強引にあの娘を。・・・・・・それ以上はちょっと、恥ずかしくて言えません」
少し、頬を赤らめる杉下さんとこの奥さん。彼女はまだ二十代後半、乙女の炎はまだまだ消えちゃいない。これからが女盛りなのだ。
「とにかく、これからが見物よね」
そう言って、川崎さんとこの奥さんは妖しげな笑みを浮かべた。
乙女の炎は鎮火したが、おばさん根性の炎は活火山の如く燃えさかっている五十手前はさすがに言うことが違う。
杉下さんとこの奥さんは思った。この人にだけは注意しきゃ、と。
「それよりも、知ってます? 最近、小火が多いんですって」
「知ってます知ってます。やっぱり、乾燥した季節ですからねぇ。うちも気を付けないと」
そんな事を話しながら二人は歩いていった。
なにはともあれ、アスカの存在はマンション町中の奥様連中に知られることとなった。かなり脚色されてはいるのだが。
現在、アスカは人買いから売られた悲運の少女と言うことになっている。
少なくとも、アスカ自身に悪い印象が出来ていないのが唯一の救いか。
カイトは暗澹たる気持ちで帰宅の途についていた。
「はぁ」
ため息をつく。背中に感じる夕陽の温かさだけが唯一の救い。
もう一度、ため息をつく。今のカイトほど冬の夕陽が似合う劣等生はいないはず。
「カエルが鳴くからかえ〜ろ」
かなり、目が虚ろ。
カイトがこんな溜め息をつく原因は優の条約破棄によるもの。
数日前に採択された『絶対無理だ宣言』を破棄したのだ。
つまり、優は幸か不幸か小説のネタを思い付いてしまったのだ。
推理物で、それなりに渋い雰囲気が出そうな気配なんだそうだ。
一方、その事をすっかり忘れて、今日の夕飯を楽しみにしていたカイトは当然、ネタ探しも何もしているはずがない。
そのカイトに対して、部長である沙耶が一つの宣言を民主主義の精神を無視して採択した。絶対書いてこい宣言である。
その時、カイトは超大国のわがままに振り回される日本のような気持ちになった。
首相、あんたはえらい。カイト的支持率1%上昇。
気付くとカイトは自分の家まで戻ってきていた。
アスカに今の思いの丈をぶつけよう。きっと、いい返事が返ってくるはず。
近所のおばさま連中に聞かれたら絶対に誤解を生む非常にまずい事を考えながら、ドアノブに手をかけた。その時、妙な物音が響いた。
後ろを振り向くと消火器が倒れていた。
何だ?あれ。
壁の影に隠れてこっちを覗き見る妙な肉の塊。
それが何であるかカイトは瞬時に理解した。さすがは大家代理。
アスカのこと探ってるんだろうな。きっと。
でも、あれで隠れてるつもりだったら、ノーベル平和賞ものだよ。
一度、ため息をつくとカイトはドアを開けた。
「ただいま〜」
リビングの方から楽しげな笑い声が聞こえる。
父さん、帰ってきたのか?
そんな事を考えながら、カイトはリビングの方に足を向けた。
「父さん、おかえ・・・・・・何だ」
和やかにこたつに入っているアスカと老人。
老人は明治時代から出てきたかのようなシャツに袴姿。
当然、有馬じゃない。
「お帰り、カイトくん」
「ただいま、アスカ」
そう言って、彼女に笑顔を見せる。
「遅かったな。さっさと着替えてこっちに来い。今、戦利品の確認をしてるところじゃ」
「う、うん」
返事をするとすぐにカイトは自室に歩いていった。
この当たり前のようにこたつに入っている老人は名を皇聖院悠三郎と言った。
彼はカイトの祖父、双樹正義の戦友であり、幼なじみでもある。
それが縁で双樹家とは家族同然の関係。
カイトにとっては祖父正義に次ぐ祖父で、彼を『じっちゃん』と呼んでいる。
そして、彼はこのマンション町中の『105号室』に住んでいる。
年齢は七十近くになる。
「じっちゃん、帰りが遅かったけどどうしたの?」
予定では昨日の夕方帰ってくることになっていた。
「何、ちょっと知り合いに会っておってな」
「じっちゃんの知り合いって、やっぱり」
「うむ。推測通りじゃ。その内、お前にも会わせてやろう」
「遠慮しておくよ。それよりもアスカ、びっくりしたろ?」
「えぇ。だって、部屋に入ったら知らない人がいるんだもん」
ここ数日でどこかぎこちなかった会話も普通になった。
時々、アスカが魔物を封印しに出かけるのだけは馴れなかったが。
「わしも驚いたぞ。カイトの部屋にこのような美少女が入ってきたんじゃからな。わしがあと十年若かったら放っておかなかったぞ」
そう言って、じっちゃんは呵々と笑った。
「しかし、カイト。お前もいつの間にか大人になったんじゃなぁ。有馬の記録を更新するとはさすがは正義の孫じゃ」
「ちょっと、待った」
制止をかけるカイトだが、それで止まるようなじっちゃんじゃない。
彼もまた違う意味で祖父正義同様に傍若無人であった。
「みなまで言うな。今回の戦利品の半分は祝いにやろう」
この『半分は祝いにやろう』でカイトは抵抗を止めた。
一方、じっちゃんは思いっ切り後悔した。勢いに乗りすぎたと。
「やっぱり、三分の、いや」
「じっちゃん」
ジト目でカイト。
「漢は一度言ったことは余程のことがない限り取り消さないんでしょ」
「う、うむ」
確かに電柱の上からそう言ったことがある。
「そうじゃ、そうじゃとも」
じっちゃんは思いっ切り滂沱した。
「どうしたんです?」
余り事情を知らないアスカは心配そうな顔をする。
「なに、心配無用じゃ。心配無用じゃとも」
涙を拭うじっちゃん。だけど、涙は止まらない。
泣きながらもじっちゃんは側の鞄から中身を取り出し、こたつの上に広げた。
「さらば、汗と涙の結晶達よ。・・・・・・じゃが、カイトよ」
「な、なに」
突然、まじめな顔で迫るじっちゃんに後ずさりするカイト。
「コピーはとるからの。いいな」
「分かったよ」
そこには数々の本が山と積まれている。広げているのに山。かなりの数だ。
同人誌だ。総数158冊。その内訳は美少女物45%、熱血物32%、オリジナル23%と言った具合だ。
じっちゃんは地方で開催される同人誌即売会に行っていたのだ。
そして、それは一つの事実を端的にあらわしている。
「でも、毎回毎回よくこれだけ集められるもんだよ」
半分感心し、半分呆れるカイトだった。
即売会の人の多さは尋常ではないことは有名だ。
「何、これもおたくを極めんとする者に秘められた特殊能力の一つよ」
顎に手を当て、角度を決め、笑みを見せる。背中に何処かで見たようなお星様が。
じっちゃんはおたくがおたくと呼ばれる前からおたくをやっている筋金入りのおたくなのだ。その証拠に彼にはこんな逸話がある。
戦争末期の事だ。当時、日本は大東亜共栄圏創立、八紘一宇を旗印に初戦は奇跡の快進撃をしていたが、時と共に勢いを失っていく。敗色濃くなった戦況を打破すべく、軍部は一つのやけくそ作戦を実行することにする。特攻である。
爆弾を抱え、敵艦へと突っ込み撃破する。
最後の武器である命を使った真の意味での最期の攻撃である。
結果、数多くの青年が碧海に散っていったのだった。
紅顔の美少年(自称)だったじっちゃんもまた特攻隊に志願、採用される。
当時、特攻隊は青少年達にとって尊敬と憧れの存在であったのだ。
そして、運命の日。
往路分の燃料しか積んでいない零戦に乗り込み、空へ。
じっちゃんは編隊を組み、敵艦隊を目指した。
この時間、彼は今までの人生を振り返っていた。
家族、生まれ育った故郷、初恋のひと、そして・・・・・・。
今まさに敵艦隊と遭遇しようとしたその時、じっちゃんの瞳に力が宿った。
・・・・・・気になる。無性に気になる!!
「のらくろの続きが気になる!!」
じっちゃんは叫びながら銃弾飛び交う中を飛ぶ零戦から脱出。
零戦は見事、敵巡洋艦に突撃、撃沈させたのだった。
その後、じっちゃんは泳いで本土まで辿り着いたそうだ。
これが事実かどうかはもはや本人しか分からない。
「ところでカイトくん」
同人誌を物色するのを止め、アスカの方に顔を向ける。
「何?」
「おたくって、何?」
無垢な顔で訪ねるアスカ。
この一言にカイトは口ごもった。
おたくって、何って言われても。
屈託の無い笑顔のアスカ。
人里離れた山奥で育ったアスカにとって俗世間の事はよく知らないのだ。
はっきり言って、カイトには説明のしようがなかった。
「カイトよ。何をそんなに悩むことがある。いいかね、アスカくん」
じっちゃんは不意に立ち上がると、こたつの上に上った。
座っているアスカを見下ろす形になる。
「おたくとは、一つの道を極めんとする求道者のことじゃ!!」
カイトはじっちゃんの背中に稲光が輝いたのを感じた。
「と言うことは日々の努力を欠かさない修練者のことですね」
「うむうむ。そうじゃ、そうじゃとも。さすがはカイトが選んだ人なだけの事はある」
じっちゃんは滂沱した。そして、すかさず窓を開ける。
「アスカくん。あれがおたくの星じゃ」
そう言って、適当な星を指さすじっちゃん。
「はい」
感動で瞳を輝かすアスカ。
まるで二昔前の熱血スポ根状態だ。
一方、カイトは二人を余所に同人誌を物色していた。
ガチャ
分けの分からなくなっている双樹家の玄関の扉が開かれた。
そこには両手一杯に買い物袋を持ち、背中からは酒瓶が顔を覗かせている人物が。
完全無欠の宴会装備である。買い物袋から見えるネギから推測するに鍋か。
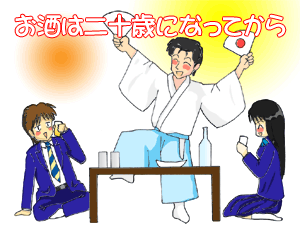 「カイト、アスカさん。いるか?」
「カイト、アスカさん。いるか?」そう言いながらドカドカと廊下を通り、リビングに顔を出した。
「ここにいたのか。おっ、おじさんも一緒か」
「おかえり、父さん」
物色する手を休めずにカイト。
「おかえりなさい」
笑顔でアスカ。
「有馬、えらく重装備じゃの」
「あぁ、少し遅れたがアスカさんの歓迎会にと思って」
そう言うと有馬は荷物を下ろした。
はっきり言ってかなりの量だ。食糧も酒量も。
「さすがは有馬。分かっておるの」
「カイト、コンロを出しておけよ。おじさんは食器の用意、アスカさんはおれの手伝いを頼むよ」
こうして、双樹家の宴会が始まったのだ。
全員の意識が無くなるのにそう時間は掛からなかった。