2
カイトの通う高校は私立林海学園と言った。
この校名は初代理事長が付けたものだ。
林間学校と臨海学校があるから、林海学園にしようと言った一言で決定した。
教師陣もその一風変わった校名に恥じない妙に濃い方々で構成されている。
授業中に脱線し、世間話を始めてしまうのはまだ序の口。
時には生徒に愚痴をこぼしたり、恋愛相談をし出す教師もいる。
校内放送で愛の告白をした教師までいるのだ。
いわゆる普通の学校では弾かれてしまうような教師が集まっているのだ。
教師陣がこんな人達で構成されていると生徒も、と思うかも知れないが、意外なことに生徒は基本的には成績優秀なのだ。
理由は簡単。こんな先生じゃ頼りない。だったら、自分でやろうと言った具合だ。
文字通りの反面教師なのだ。
だが、それに乗らない者も当然いる。カイトだ。
普段から授業中、眠っているカイトだが今日に限って起きていた。
珍しいことをした反動かどうかは知らないが、彼は今、不思議な光景を目にしていた。
ボク以外、みんな寝てる?
カイトは両隣の人の顔を覗き込んでみる。
寝てる。熟睡状態だ。気持ち良さそうな寝息を立てている。
鼻の穴に指を突っ込んでみたくなる衝動を必死でカイトは抑えた。
普段なら熱弁を振るって世間話している総合理科の教師は立ちながら眠っている。
ボクにはあれは出来ない。
と、妙な関心をするカイト。
少し、席を立つのが不安だったがカイトは意を決して、立ち上がった。
そして、斜め前の優のところに行く。
優はしっかりと目を開け、教師の方に顔を向けている。
「優、優」
小声で呼び掛けてみるが、反応無し。
「優、優ってば!」
恐る恐る身体を揺すってみるが、反応無し。
もう少し、カイトは強く揺すってみたが、やっぱり反応無し。
「うるさいぞ、カイト!」
優の一喝に驚いたカイトだったが、事態が事態なだけにカイトは怯まず話しを先に進めた。
「優、みんな変なんだ」
カイトの訴えも聞かず、優は始めと同じ体勢に戻った。寸分違わぬ体勢に。
その時になって、カイトは気付いた。優が気持ちよさそうな寝息を立てていることに。もっと、早く気付けよ。
「優が・・・・・・寝てる。授業中に!?」
カイトは信じられないものを見るかのように数歩後ずさった。
「ただごとじゃない!」
授業中、絶対に寝ることの無い優までもが眠っている。
例え、教師の無駄話だろうと愚痴だろうと愛の告白であろうと眠らない優がだ。
シャーペンを手にしながら。しかも、目を開けたまま。
ようやく、この非常事態に気付いたカイトはあたふたと走り回った。
三周ほどで息切れしたカイトは他の教室が気になった。
「もしかして、他の教室も?」
カイトの頭の中にはからかわれているのではと言う発想はない。
元来、自分を疑っても他人を疑わない性格なのだから。
恐る恐る教室を出た。
廊下は信じられないほど静かだった。
世間話の声も、唯一まともな体育の授業の声も聞こえてこない。
音を出すのが申し訳ないと思うほど静かだ。
水を打ったような静けさとはこう言うのを言うのだろうか。
緊張した面持ちでカイトは隣りの教室を覗いた。
やっぱり、そこも全員眠っている。
「なんてこった」
カイトは両手を頭に持っていった。
「起きているのはボクだけだ!!」
カイトの絶叫が廊下に鳴り響いた。
普段なら、うるさいぞと言う声が返ってくるはずなのだが、返ってくるはずもなく。その代わりに。
ぐおおぉぉぉっ!!
アニメやゲームに出てくるような地の底から湧き出てくるような咆吼が返ってきた。動物園に行ってもこんな咆吼は聞けない。
やっぱり、ただ事じゃない。
カイトは思い当たることがないか必死に脳を回転させた。
授業中、居眠りしていたのがいけなかったのかな。
違う違う。あんな事で神様が怒るはずがない。
だったら・・・・・・あんな可愛い娘に抱きつかれたのが原因?
・・・・・・・・・・・・可愛かったなぁ。
こんな時にもドキドキしている自分に少し情けなくなるカイトだった。
ぐおおおぉぉぉっ!!!
再び咆吼が校舎の窓ガラスを振るわせる。
「怖いけど」
カイトは銀行の利子ほどの勇気を奮って窓の外を覗いた。
そこにはサファリパークにいるライオンよりも少し大きめの灰色の何かがいた。
カイトの脳裏にテレビで見た狼の姿が浮かび上がったが、それとは全然違う。
針のような輝きを放つ獣毛に近づく者を引き裂きそうな爪、そして、紅玉の様な真っ赤な瞳。
その瞳がこっちを見た。
目と目で通じ合う? ・・・・・・わけない!!
カイトは心臓が鷲掴みにされた様に硬直した。
逃げ出したいのに動けない。叫び声すらも出ない。
それは一度、咆吼を上げるとカイトのいる三階に向かって飛び掛かってきた。
「わぁぁぁぁっ!!」
土壇場になってようやくカイトの身体が動いた。
それから、すぐにカイトの背後で壁が壊される音が聞こえる。
「ひぃぃぃぃぃっ!」
カイトは情けない声を上げながら、どうにか廊下の踊り場までやってきた。
そして、素早く身を隠す。
後ろから襲ってくる気配はない。
カイトは恐る恐る顔を出した。
そこには見事に顔だけはまった怪物が藻掻いていた。
怪物は思っていたよりも大きかった。
はまっている顔だけでもカイトの身長の半分程もある。
全長は推して知るべしと言ったところか。
怪物は首を振って、爪で壁を掻き、どうにか校舎内に入ろうとしている。
が、日本の建築技術の前にかなりの苦戦を強いられていた。
首だけで藻掻く。これはかなり間抜けな姿だ。だけど、それを笑ってられない。
今後の事を考えなくちゃいけない。
はずなのにその間抜けな姿にカイトはホッと一息ついてしまい、全然別の方向に思考が働いてしまい、とある事が頭をよぎった。
あの怪物と似たものを何度かカイトは見ていた事を思い出したのだ。
ゲームの中で。
「ケルベロスだ。きっと、本気を出すと凄い金切り声を上げるんだ」
地獄の番犬。青銅の声を持つ冥王の魔犬。
しかし、青銅の声って一体。
黒板に爪を立てて引っ掻いたような声なのかもしれない。
そんなバカな考えがカイトの頭を駆け巡っていたその時、不意に彼の肩をポンと叩く者がいた。
「のわぁぁぁっ!」
あまりの驚きにカイトは階段から見事に転げ落ちた。
ボールを転がしてもここまで見事に転げ落ちないだろう。
「大丈夫ですか。勇者様」
「は、はははっ」
カイトは乾いた笑いをしながら、ひっくり返っていた。
踊り場から少女が心配そうにカイトを見下ろしていた。
あのカイトの事を『勇者様』と呼ぶ少女が。
「ホントに大丈夫ですか?」
少女は階段を駆け下り、カイトの顔を心配そうに覗き込んだ。
やっぱり、可愛いなぁ。
「大丈夫ですか? 少し、赤くなってますけど」
「な、何でもないよ」
「よかった」
カイトは少女の差し出された手に掴まって起き上がった。
「でも、頭から落ちたのに」
「これ以上、バカにならないから大丈夫だよ」
「ふふっ」
少女は冗談だと思ったみたいだが、実際そうだから困ったものだ。
何となく照れくさくて、カイトも笑う。
和やかな雰囲気が踊り場に生まれた。
だけど、そんな雰囲気が長く続くはずもなく。
突然、壁が崩れる音が廊下に、いや、校舎全体に響き渡ったのだ。
二人は仲良く廊下の壁から顔を出した。
あの紅い目がこっちを見ている。
明らかな敵意の目だ。
でも、首を突っ込んだままの体勢は変わらない。いや、肩口まで入ったか。
「何でだよ。自分から突っ込んでいったのに」
カイトは分けの分からないことを叫んだ。
「勇者様、こっち」
「えっ!?」
カイトは少女の引っ張られるまま階段を上へ上へと上っていった。
時折、振動で階段が揺れる。その度にカイトは階段を踏み外しそうになった。
それでも何とか上へと上がっていく。
「ねぇ。一体、あれ何なの」
「魔物です。魔が蘇りつつあるんです」
「そんな使い古されたゲームネタみたいな」
「現に!?」
少女が説明をしようとすると、再び強い振動が起こり、カイトはその拍子に再び、階段から転落した。これまた、見事に頭からだ。
これで頭が良くなったらいいのにと、痛い頭をさすりながらカイトは思った。
どこまでもお気楽なヤツである。
だが、そんなお気楽な思考は次の瞬間ブッ飛んだ。
カイトの目と鼻の先に少女の顔があったのだ。
お互いの心臓の鼓動が聞こえるほどの密着状態。
「あの・・・・・・大丈夫?怪我は?」
「はい、勇者様が守ってくれましたから」
「そう。良かった」
心の底から安堵した笑みをカイトは浮かべた。
「ごめんな。転んだのに巻き込んで」
「いえ・・・・・・そんな」
少女は少し、俯いてそれだけ言った。
少し顔を赤らめていたのをカイトは気付かなかった。
それよりも、少女に怪我をさせなかった事を本当に安堵していた。
再び、壁が崩れる音がした。ほぼ真下からだ。
あの怪物が狭いながらも必死で階段を上ってきているのだろう。
さっきまで顔を赤らめていた少女もその音にハッとし、再びカイトの手を取って上へ上へと階段を駆け上がっていった。
階段を上っていけば、行き着く先は当然屋上。
屋上に飛び出したカイト達は巧く形容しようがない光景を目にした。
遊園地でも万国博覧会でもこんな光景はお目にかかれない。
お薬の『お』を『ま』に代えたものを使えば見れるかも知れないが。
「歪んでる?」
そう言って、カイトは自分の身体も同じように曲げてみたが、変化無し。
歪んだガラスで出来た蓋を学校に覆っている。そんな感じだ。
異常現象はそれだけではなかった。
まだ、昼前だと言うのに空は真っ赤に染まり、全てを覆っている。
夕日の様な赤さだが、陽の光によるものじゃない。
空には雲一つない。太陽すらも。
でも、真っ赤に染まっている。
「何、これ」
あまりにもベタな問いの答えは返ってこない。
その代わりに別のものが返ってきた。
崩れる音。
二人が出てきた屋上の扉付近が崩れたのだ。
その瓦礫が持ち上がり、あの怪物が姿を現した。
身体を振った拍子に砂煙が立ち上がる。
「ごほっごほっ」
咳き込む二人。
ホントは咳き込むどころじゃないんだけど、これは仕方がない。
ようやく、煙がおさまると、そこには身体を低くして、何時でも襲い掛かる体勢で構えている怪物の姿があった。
だが、体中傷だらけな上に長い舌を垂らし、荒い息をしている。
狭い階段をコンクリートの壁を破壊しながら上ってきたのは相当な労力だったのだろう。怪物は満身創痍だった。
それでも怪物は攻撃の意思をその紅い瞳に宿している。
その瞳と目が合ったその時、カイトの脳裏に何者かのメッセージが届いた。
動物と接するときは決して怖がったり、敵意を持ってはいけないんですねぇ。
そう、日本が世界に誇る動物翻訳人ムツゴロウさんからのメッセージだ。
毅然とした態度で敵意が無いことを知らせてやれば、こ〜んな事も出来るんですよぉ。
そう言って、ムツゴロウさんは野生ライオンの口の中に顔を突っ込む。
ほ〜ら、大丈夫でしょう。あなたもやってみて下さい。
「ンな事出来るかぁぁっ!!」
「勇者様!?」
突然のカイトの叫びに怪物も一瞬だけ怯んだ。が、一瞬だけだから意味はない。
紅い瞳が敵意から殺意へと変わったのをカイトは何となく感じだ。
まさに火に油。天ぷら火災の如く、一気に燃え上がった。
怪物は一気に駆け出した。バカみたいに大口開けて。
カイトは怪物から少女を護るような形で立ちふさがった。
「ダメです、逃げて下さい。まだ、覚醒してらっしゃらないのに!」
少女の意味不明の言葉にもカイトは動かなかった。
いや、動けなかったのだ。
ホントは少女を連れて、逃げ出したいのだが、恐怖で足が竦み、身体が動かなくなっているのだ。その顔には引きつり笑いが張り付いていた。
一方、カイトの背に護られていた少女は意を決した表情をし、カイトから離れた。
決して、見捨てた理由じゃない。
怪物の口がカイトのすぐ目の前まで迫った。
一月二十日、水曜日。この日がボクの命日か。・・・・・水曜日?水曜日!!
カイトの目が急にカッと見開かれ、普段の彼では信じがたい速度で避けた。
突然のカイトの行動に怪物は勢いを殺すことが出来ずに前のめりに倒れ、コンクリートと接吻することに。
「いまだ!」
少女の手が金色に発光し出し、それを怪物に向けて照射した。
怪物は光に包まれ、苦しげな咆吼を上げる。
苦しげに悶え苦しむ鳴き声が上がり、それと同時に煙が上がる。
今度はさすがに二人とも咳をしなかった。それどころじゃない。
苦悶の鳴き声が収まると同時に煙りも風に流されていった。
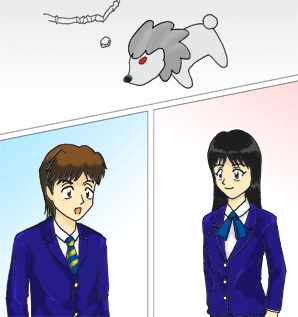
怪物のいた場所には一つのぬいぐるみが落ちていた。
可愛らしい狼のぬいぐるみが。ラブリ〜わんわんだ。
「勇者様、大丈夫ですか?」
少女はカイトの元に駆け寄ると彼の手を取って起こした。
「うん、何とか。前の時間、トイレに行って置いて良かった」
冗談抜きでカイトはそう思った。
「でも、さすがです。ご自分が魔物の囮になって、私に封印のチャンスを作って下さるなんて」
「ははっ、結果オーライかな。二人とも無傷で良かった」
と、一応話しを合わせるカイト。
「はい。ホントに良かったです」
そう言って、少女はぬいぐるみを拾い上げ、笑みを浮かべた。
そこでカイトの意識は途切れた。
身体を揺すられる感じがして、カイトの意識は潜水艦のように急浮上した。
海面の状況を知るために潜望鏡を上げるように、まず聴覚が起きた。
「おい、双樹。おい」
「ふみ?」
「ふみ?じゃないだろ」
そこには総合理科の教師の顔があった。
お互いの吐息が感じられるような距離に。
「のわっち!」
仰け反った拍子に椅子ごと倒れそうになったが、何とか耐える。
「折角、先日やったスカイダイビングの話しをしてやってるって言うのに」
やっぱり、授業をやらずに無駄話をしていた。
いや、等加速度運動の説明をスカイダイビングを例にしたいのかもしれない。
そう言えば、前はバンジージャンプの体験談だったっけ、段々、上に向かってるなぁ。今度は衛星軌道上からのジャンプなんてやんないだろうな。
・・・・・・この人ならやりかねん。
と、カイトは思った。
そして、彼の口は思ったことをすぐに口にしてしまった。
「先生、今度は衛星軌道上からジャンプしようなんて思ってないですよね」
「双樹、良い事言うじゃないか。そうか、衛星軌道上からのジャンプか」
総合理科教師は口端を緩めた。その瞳には危険な輝きを宿っていた。
マズイ事言ったかな。・・・・・・まぁ、いいか。どう足掻いても衛星軌道上にはいけないし。
一週間後、彼が種子島のロケットを使って本当に実行しようとして、驚く事になるとはカイトはまだ知らないのだった。それはさておき。
「褒美に一問、問題をやる。答えられたら、お祝いをやろうじゃないか」
お祝い 林海学園用語の一つ。平常点以外の秘密の点数。
秘密のはずだが、何故か公然と行われている。
「太陽よりずっと質量のある恒星が死を迎えるとき、超新星爆発が起こるのは覚えてるよな」
カイトは頷いた。前の問題と答えがこれだった。
「じゃ、実際に超新星爆発を起こすのは太陽の何倍以上の質量だと言われているか」
「三倍以上」
事も無げにカイトは答えた。
「ついでだ。十倍以上の質量の恒星が死を迎えると超新星爆発とどんな現象が起こる言われている」
「ブラックホールが発生する」
即答だった。
決して、勘ややけくそで答えているわけじゃない。
事実、カイトはこのお祝いだけで一年から二年に進級したある意味での強者なのだ。普段はナルトの様な脳みそくんも、この手のネタだけは豊富に吸収していた。
「・・・・・・なぁ」
教師はジト目でカイトを見た。
「はい?」
「何で、そんな知識を持ってるのに何時も赤点なんだ?」
「何でって言われても、ボクにも見当がつきませんよ」
カイトは自分の脳みその音と同じ様にカラカラと笑った。
「まぁ、いいか。それよりも、もう寝るなよ。勇者様」
勇者様の部分が特に強調された。彼も今朝の事件を知っていたのだ。
林海学園教師陣はこのネタが異常に好きだ。電光石火で情報は広がる。
もし、生徒同士で子どもが出来てしまっても、学校を上げておめでとうパーティを計画、実行する。それどころか、双方の両親を説得し、見事納得させるはずだ。
そんな、熱血精神を持つ教師の一言で教室の空気は止まった。
凍り付いたと言った方が正しいかも知れない。『勇者様』と言う単語に。
今朝の事件はカイトを知る人々によってエイトマンも真っ青な速度で広がった。
その現場を目撃した者も数名いる。事実だ。揺るがない事実なのだ。
からかいと祝福と妬みのネタになるはずなのだが、カイトにそのネタをふる者は誰一人としていなかった。ネタをふる=それを認めると言う方程式があるからだ。
確かにカイトは勇者だ。オールペンギンさんを取ったヤツなんてそうそういない。
だからと言って、そんな理由でいきなり見ず知らずの少女がカイトに抱きつくなんて事は考えられない。
しかし、事実なのだ。磁力は同じ極同士は反発し、異なる極同士は引きつけ合う。
では、なぜこうなるのか説明できる学者はいない。でも、事実。それと同じだ。
だが、その事実を受け入れられる者は一人としていなかった。
この異常事実の解明の為、秘密裏に発足した委員会は以下のような推測を立てた。
川で溺れていたところを助けたとか、車に轢かれそうになったところを助けたなどの救出劇説。が、それは絶対にあり得ないので却下。
川に飛び込めば確実に海まで流され、暴走車から人を救おうとすれば自分が轢かれるのがカイトだからだ。
次いで出た一目惚れ説。速攻で却下。
基本的に温厚でお人好しの性格は好感を持って迎えられるが、一目惚れの絶対必要条件が欠けている。カイトは美男子ではない。
皆にとって、カイトが女の子に抱きつかれた事実を受け入れるよりもは、即席解脱者の空中浮遊の方が、受け入れやすかった。
そんな皆の思いを余所に当事者のカイトは一人呟いた。
「みんな、寝てたんじゃないの?」
『は?』
教室は巨大なクエッションマークに占領されてしまった。